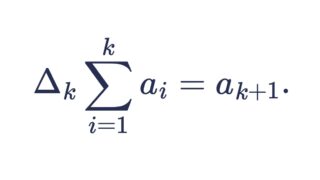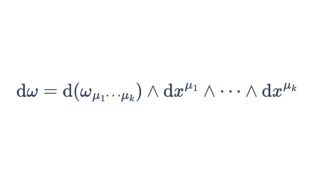即興で書いた短編を公開するシリーズ、「即興文学」です。
今日は「閉鎖病棟のふたご座流星群」をお届けします。
本文
「ちょっと話したいことがあるんだけど、いいか」
担任が私に声をかけてきた。
「どんな話なんですか?」
「後で話す。放課後、美術準備室に来い」
私は「なんで美術準備室?」と思った。
放課後美術準備室に行くと、担任が待っていた。
「すみません、話ってなんですか?」
彼は部屋の鍵をかけた。
「まさか、話があると思ってきたのか?今日は話なんてない。お前を襲うために呼んだ」
私はそれで全てを察した。
だが、もう逃げられなかった。
それから私は力づくで服を脱がされていった。
必死で暴れた。
でも、だめだった。
されるがままにされた。
そこから先はよく覚えていない。
気づけば私は西日が差し込む部屋の中、天井を見上げていた。
何も感じなかった。
家に帰って真っ先にシャワーを浴びた。
夕食は食べれなかった。
翌日、私は布団の中でうずくまっていた。
「もう学校の時間だよ!早くしなよ!」
母親がリビングで私を呼んでいる。
私は制服に着替えて、なんとか学校に行こうとした。
玄関で靴を履こうとした瞬間、昨日の風景が白昼夢のように現れた。
私は過呼吸になっていた。
「どうしたの?体調悪いの?」
母親は心配していた。
だが、何も言えなかった。
私は部屋に逃げこんだ。
そして布団をかぶり、涙を流した。
声は出なかった。
ただ、枕がすごい勢いで濡れていった。
気づけば私は部屋のベランダに立っていた。
ここは4階。
「すべてを終わりにしよう」
私の手は異常なほど震えていた。
空は晴れていた。
私はその景色を眺めた後、柵に手をかけた。
そして柵を乗り越えた。
その瞬間、私は重力を感じなくなった。
目をつぶっていたが、ものすごい音の風が聞こえた。
----------
「ここは、どこ?」
見上げると、白い壁があった。
「もしかして、また美術準備室!?」
私は暴れ出した。
だが、左腕に針が刺さっていた。
後ろを見ると、モニターに数字が表示されていた。
「もしかして、病院?」
前には医師がいた。
「目を覚まされたんですね。本当によかったです。あなたは4階から転落して、しばらく意識がなかったんですよ」
私はなんとなく思い出した。
「結局死ねなかったじゃん」
私は今すぐ病室を抜け出してまた飛び降りてやろうかと思った。
「ただ、これからも命の危険があると判断されました。親御さんの同意を得て、医療保護入院となりました。体調が回復するまでは退院できないです」
ショックだった。
「え、出られないんですか?」
「はい。今退院しても、…」
私はぼーっとしていた。
医師は去っていった。
そこからしばらく、ベッドに固定されたままの生活が続いた。
スマホは使わせてもらえなかった。
「こんなところにいて、なんの意味があるんだろう。あのとき死んでいたほうがずっとマシだった」
そんな虚無の日々が続いた。
手足が動かせず、動かないマネキンのようにずっと寝ていた。
何もする気になれなかった。
病室のカーテンは開けないでほしいとだけ言っておいた。
その後、私は骨折した手足や肋骨の手術を受けた。
「すべての手術が終わったよ。よかったね」
看護師が私にそう言った。
「べつに。なんもよくない。あのとき死んでればよかった」
彼女は悲しそうな表情をしていた。
それから私は精神科医の治療を受けることになった。
だが、ずっともやもやして治療を受ける気はなかった。
彼女は毎夜、私の病室にやってきた。
何も言えなかった夜でも、ただ私の手を握ってくれた。
だが、それすらつらかった。
あるとき、私の目に西日が入ってきた。
私はすべてを思い出した。
私は過呼吸になり、その場で倒れ込んでしまった。
「大丈夫!?」
看護師が駆けつけた。
私は口をぱくぱくさせるだけで何も言えなかった。
手が異常なほど波打っていた。
その夜、彼女が私の病室にやってきた。
「今日は大変だったね」
私は黙った。
「私の気持ちなんて、あんたにわからないでしょ」
彼女はしばらく黙っていた。
「うん。私には、あなたの苦しみは全くわからない。想像することもできない。でも、ただ隣にいることはできる」
私は重い口を開いた。
「べつに、寄り添ってもらおうとか思ってない。私は今すぐ死んでしまいたい」
少しの間沈黙が流れた。
「今日はふたご座流星群の日なんだよ。屋上、行ってみる?」
私はびっくりした。
今まで屋上なんて行ったことがなかった。
「屋上なんて、行かせてもらえないでしょ。私はすぐ死のうとするから」
「そうだよ。普段だったら屋上には行けないよ。でも、今日はふたご座流星群だから特別に見てもらいたいと思って。私が一緒なら医師もいいって言ってた。連れていってあげる」
私は「また飛び降りるチャンスだ」と思った。
だが、今私は車椅子生活をしていて足が思い通りに動かなかった。
きっと屋上に行っても死ねないだろう。
「やっぱり興味ない。流星群なんてどうでもいい」
私は視線をそらした。
「今年は月がいなくて、流星の数も多いんだってさ。最高の条件なんだよ。来る?」
看護師はしつこく私に勧めてきた。
「まあ暇だし。行くだけ行ってみるよ」
「ありがとう。じゃあ連れていってあげる」
私は車椅子で運ばれ、専用エレベーターに乗せられた。
扉が開くと、そこは別世界だった。
「すごい、今まで外なんて見たことがなかった」
あたりは真っ暗だった。
遠くのほうに街明かりが見えるくらいだった。
「今日は晴れてるよ」
私が空を見上げると、そこには無数の光の点が光っていた。
「すごい…」
私はしばらくその姿を眺めていた。
地平線のほうを見ると、一際目立つ星座があった。
「あの砂時計みたいなやつはなに?」
「あれはオリオン座だよ」
「初めて見た…」
左上だけ赤っぽかった。
そこから視線を上にあげていくと、また明るいオレンジ色の星が見えた。
「あれは何?オレンジ色の明るいやつと、周りにつぶつぶがいっぱいあるよ」
「あれはヒアデス星団。オレンジ色の明るい星はアルデバランっていうんだよ」
私はしばらくその姿を見ていた。
「さらにその上にはすばるがいるよ。見える?」
アルデバランからさらに上のほうに行くと、青っぽいキラキラがあった。
「あの青っぽいやつがすばる?」
「そうだよ」
「綺麗だね」
私はその姿をまた、しばらく眺めていた。
すばるはヒアデス星団とは少し違い、なんかキラキラしていた。
その姿が宝石のようで、ただただ美しかった。
そのとき、明るい光の筋が頭上を流れていった。
すばるの横をかすめていった。
「お!流れた!」
彼女が大きな声をあげた。
「え、今流れたよね?あれが流星群?」
「そうだよ。これから何十個も流れてくと思う」
私はまた、すばるのほうに目線をやった。
それから私たちは10個以上の流れ星を見た。
その度に私たちは大はしゃぎした。
「もうそろそろ消灯時間だね。帰ろっか」
「あ、そっか。さすがに一晩中は見れないよね」
「うん、これからがいい時間帯なのにね」
彼女の声は悲しそうだった。
「星は好きになった?」
「うん。綺麗だった」
私はすばるをずっと眺めていた。
「もし星が見たいっていうなら、毎日ここに連れていってあげるよ。でも、ひとつ約束をしてほしい」
私は彼女のほうを向いた。
「今まで精神科医の治療、受けたくないって言ってたよね。確かに、治療を受けると過去のトラウマに向き合わないといけなくなる。それってすごくしんどいと思う。つらいと思う。でも、これから前に進むのに必要なステップなんだ。つらいときはまた星を見せてあげるよ。どう?明日は精神科医の人と話してみる?」
私は黙った。
精神科の治療は怖そうだった。
「もっと私が壊されるのでは」と心配だった。
でも、また星が見られるのなら…
私は口を開いた。
「わかった。明日は10分だけならいいよ」
彼女は笑顔になった。
「えらいね。でも無理しなくていいよ。ここは安全だから、少しずつ歩いていけばいいよ」
私は何も言わなかった。
視線をすばるのほうに戻した。
そのとき、今までより遥かに明るい、緑色の流れ星が流れていった。
「え!今めっちゃ明るいの流れた!すごいよ!」
「うそ?まじ?私見れなかったんだけど…」
彼女は残念がっていた。
それから私たちは病室に戻った。
その日の夜は、久しぶりに夢を見なかった。
何も見ず、ただ安らかに眠れた。
朝が来た。
少しだけ、ほんの少しだけ「生きていてもいいのかな」と思った。