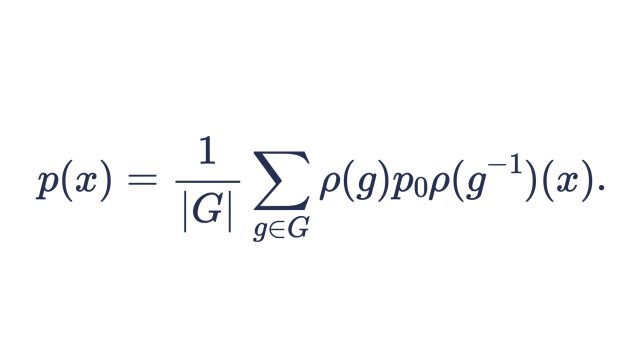微分幾何の勉強は難しいですよね。
「外微分って何?抽象的な定義しか出てこない…」
「わかりづらすぎて泣きそう」
そんな人のために、今回は外微分の解説記事を書いてみました。
外微分って何? 外微分のライプニッツ則って何? なんで \(\text{d}^2=0\) なの? ベクトル解析との関係は? これらの疑問に全て答えていきます。
できるだけわかりやすいように細かく書きました。
ぜひ最後まで読んでみてください。
全微分から復習 まず、外微分とは何なんでしょうか?
そのためには全微分を復習しないといけないです。
関数 \(f(x,y)\) があったとき、その全微分は
\[ \mathrm{d}f(x,y)= \frac{\partial f}{\partial x} \mathrm{d}x+\frac{\partial f}{\partial y} \mathrm{d}y \]
で表されましたね。
変数が増えても同じで、関数 \(f(x^{1},\cdots, x^{m})\) の全微分は
\[ \mathrm{d}f(x^{1}, \cdots, x^{m}) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial x^i} \mathrm{d}x^i \]
と表されます。
\(x^{1}\) は累乗ではなく、1番目の座標という意味の上付き添字です。
本当はこのままシグマ記号を使って説明していきたいのですが、数学の教科書はめんどくさがりなものが多いです。
特に、「アインシュタインの縮約記法」は初心者を大混乱させる諸悪の根源ですね。笑
慣れれば非常に便利なので早いうちに慣れちゃいましょう。
アインシュタインの縮約記法 アインシュタインの縮約記法というのは「上下に同じ添字が登場したら足していると思え」というものです。
たとえばこれですね:
\[ \frac{\partial f}{\partial x^\mu} \mathrm{d}x^\mu = \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial x^i} \mathrm{d}x^i. \]
ここでは \(\mu\) がダミー添字で、\(1\) から \(m\) まで足されていることを意味します。
「シグマ消えたんだけど!?意味不明!」と言いたくなる気持ちもわかりますが、多くの教科書はこのルールで書かれているので仕方ありません。
ただ、この縮約記法は非常に便利なんですよね。
私も最初は「こんな気持ち悪い記法、絶対使わない」と思っていましたが、徐々にその便利さに惹かれて好きになっていきました。
今では縮約記法を使いまくっています。
というわけで、この記法には慣れるしかありません。
また、\( \dfrac{\partial}{\partial x^{\mu}} \) は \(\partial_\mu\) と略記されます。
いちいち書いてるとだるいからです。
なので \(\partial_\mu f \, \mathrm{d}x^\mu \) と書いてあったら \( \displaystyle \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial x^i} \mathrm{d}x^i \) を表します。
もう跡形もなく省略されてますね…
慣れると便利なので早く慣れましょう。
この記事でも縮約記法は使いますが、使わないバージョンの説明も書いていくので心配しないでください。
微分形式を簡単に復習 微分形式の定義をここで詳しく書くと面倒なので簡単に復習します。
微分形式とは関数や全微分の一般化で、3変数で説明すると次のような感じです:
\(0\)-形式:滑らかな関数 \(f(x,y,z)\) \(1\)-形式:\(f \mathrm{d} x + g \mathrm{d} y + h \mathrm{d} z\) \(2\)-形式:\(f \mathrm{d} x \wedge \mathrm {d} y + g \mathrm{d} y \wedge \mathrm {d} z + h \mathrm{d} z \wedge \mathrm {d} x \) \(3\)-形式:\(f \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z\) ここで \( \wedge \) はウェッジ積(または外積)で、常に次の性質を満たします:
(1)多重線形性
任意の \(i\) に対して
\[ \mathrm{d} x^{1} \wedge \cdots \wedge (f \mathrm{d} y^{i} + g \mathrm{d} z^{i}) \wedge \cdots \wedge \mathrm{d} x^{m} = f \mathrm{d} x^{1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d} y^{i} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d} x^{m} + g \mathrm{d} x^{1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d} z^{i} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d} x^{m} \]
(2)交代性
任意の \(i, j\) に対して
\[ \mathrm{d} x^{1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d} x^{i} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d} x^{j} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d} x^{m} = -\mathrm{d} x^{1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d} x^{j} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d} x^{i} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d} x^{m} \]
この2つの性質は微分形式で最も大事なものです。
必ずおさえましょう。
また、\(m\)変数の微分形式を簡潔に表すには縮約記法を使うのが便利です。
実際、\(m\)変数の\(k\)-形式は次のように表されます:
\[ \omega_{\mu_1 \cdots \mu_k} \mathrm{d} x^{\mu_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d} x^{\mu_k}. \]
これで「意味不明」「やばいやつだ」となる人が続出します。
縮約記法を使わず書けば、
\[ \omega_{\mu_1 \cdots \mu_k} \mathrm{d} x^{\mu_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d} x^{\mu_k} = \sum_{\mu_1=1}^m \cdots \sum_{\mu_k=1}^m \omega_{\mu_1 \cdots \mu_k} \mathrm{d} x^{\mu_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d} x^{\mu_k} \]
です。
\(\mu_1\) から \(\mu_k\) まですべてがダミー添字であり、愚直に書くとシグマの量がエグいことになります。
なので「上下に入っているやつは省略できる」ということで縮約記法が生まれたんですね。
ただ、実際には添字の中でひとつでも同じ値があったらすべて \(0\) になります。
交代性により \(\mathrm{d} x \wedge \mathrm{d} x = -\mathrm{d} x \wedge \mathrm{d} x\) なので、 \(\mathrm{d} x \wedge \mathrm{d} x=0\) となります。
従って微分形式はこうとも書けます:
\[ \omega_{\mu_1 \cdots \mu_k} \mathrm{d} x^{\mu_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d} x^{\mu_k} = \sum_{1 \leq \mu_1 < \cdots < \mu_k \leq m} \omega_{\mu_1 \cdots \mu_k} \mathrm{d} x^{\mu_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d} x^{\mu_k}. \]
ただ、表している値は両方同じなので正直どっちでもいいです。
これからは縮約記法で表していきます。
外微分とは? というわけで外微分の定義を紹介する準備が整いました。
定義はこうです:
定義
微分形式 \(\omega=\omega_{\mu_1 \cdots \mu_k} \mathrm{d} x^{\mu_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d} x^{\mu_k}\) の外微分 \(\mathrm{d} \omega\) を次で定義する:
\begin{eqnarray}
\mathrm{d} \omega &:=& \mathrm{d}(\omega_{\mu_1 \cdots \mu_k}) \wedge \mathrm{d} x^{\mu_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d} x^{\mu_k} \\
&=& \partial_{\nu} \omega_{\mu_1 \cdots \mu_k} \, \mathrm{d} x^{\nu} \wedge \mathrm{d} x^{\mu_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d} x^{\mu_k} \\
&=& \frac{\partial \omega_{\mu_1 \cdots \mu_k}}{\partial x^{\nu}} \mathrm{d} x^{\nu} \wedge \mathrm{d} x^{\mu_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d} x^{\mu_k} \\
&=& \sum_{1 \leq \nu < \mu_1 < \cdots < \mu_k \leq m} \frac{\partial \omega_{\mu_1 \cdots \mu_k}}{\partial x^{\nu}} \mathrm{d} x^{\nu} \wedge \mathrm{d} x^{\mu_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d} x^{\mu_k}.
\end{eqnarray}
外微分は常に線形性を満たすものとする。
ここで、\(\mathrm{d}(\omega_{\mu_1 \cdots \mu_k})\) は \(\omega\) の全微分で \(1\)-形式です。
これだけだとよくわからないですね。
具体例で計算してみましょう。
問題
\( x^2 \mathrm{d} x \) の外微分を計算せよ。
解答
\begin{eqnarray}
\mathrm{d}(x^2 \mathrm{d} x) &=& \mathrm{d}(x^2) \wedge \mathrm{d} x \\
&=& 2x \mathrm{d} x \wedge \mathrm{d} x \\
&=& 0.
\end{eqnarray}
問題
\( -y \mathrm{d} x + x \mathrm{d} y \) の外微分を計算せよ。
解答
\begin{eqnarray}
\mathrm{d}(-y \mathrm{d} x + x \mathrm{d} y) &=& -\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}x + \mathrm{d} x \wedge \mathrm{d} y \\
&=& 2 \mathrm{d} x \wedge \mathrm{d} y.
\end{eqnarray}
問題
\( (x+y)\sin(z) \mathrm{d} x \wedge \mathrm{d} y \) の外微分を計算せよ。
解答
\(f, g\) がスカラー関数のときの全微分の性質 \( \mathrm{d}(fg) = \mathrm{d}f \cdot g + f \cdot \mathrm{d} g\) より
\begin{eqnarray}
\mathrm{d} ((x+y)\sin(z) \mathrm{d} x \wedge \mathrm{d} y) &=& \mathrm{d}((x+y)\sin(z)) \wedge \mathrm{d} x \wedge \mathrm{d} y \\
&=& \sin(z)(\mathrm{d}x + \mathrm{d}y) \wedge \mathrm{d} x \wedge \mathrm{d} y + (x+y) \mathrm{d}(\sin(z)) \wedge \mathrm{d} x \wedge \mathrm{d} y \\
&=& (x+y) \cos(z) \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \\
&=& -(x+y) \cos(z) \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}z \\
&=& (x+y) \cos(z) \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z.
\end{eqnarray}
このように、\(k\)-形式の外微分は\( (k+1) \)-形式になります。
外微分のライプニッツ則 ここからは外微分で大事な公式を紹介していきます。
ひとつ目が外微分のライプニッツ則です:
定理
\(\omega\) を \(k\)-形式、\(\xi\) を \(l\)-形式とする。次が成り立つ:
\[ \mathrm{d}(\omega \wedge \xi) = \mathrm{d} \omega \wedge \xi + ( -1)^k \omega \wedge \mathrm{d} \xi. \]
\( ( -1)^k\) がいるので完全なライプニッツ則ではないですね。
というわけでこれを証明しましょう。
問題
\(\omega\) を \(k\)-形式、\(\xi\) を \(l\)-形式とする。次を示せ:
\[ \mathrm{d}(\omega \wedge \xi) = \mathrm{d} \omega \wedge \xi + ( -1)^k \omega \wedge \mathrm{d} \xi. \]
解答
局所座標で計算する。
\(\omega=\omega_{\mu_{1} \cdots \mu _{k}} \text{d} x^{\mu_{1}} \wedge \cdots \wedge \text{d} x^{\mu_{k}}\) および \(\xi=\xi_{ \nu_{1} \cdots \nu _{l}} \text{d} x^{\nu_{1}} \wedge \cdots \wedge \text{d} x^{\nu_{l}}\) とすると、
\begin{eqnarray}
\text{d} (\omega \wedge \xi) &=& \text{d} \left( \omega _{ \mu _{1} \cdots \mu _{k}} \xi _{ \nu _{1} \cdots \nu _{l}} \text{d} x^{\mu _{1}} \wedge \cdots \wedge \text{d} x^{\mu _{k}} \wedge \text{d} x^{\nu _{1}} \wedge \cdots \wedge \text{d} x^{\nu _{l}} \right) \\
&=& \frac{\partial}{\partial x^\rho} (\omega _{ \mu _{1} \cdots \mu _{k}} \xi _{ \nu _{1} \cdots \nu _{l}}) \text{d} x^{\rho} \wedge \text{d} x^{\mu _{1}} \wedge \cdots \wedge \text{d} x^{\mu _{k}} \wedge \text{d} x^{\nu _{1}} \wedge \cdots \wedge \text{d} x^{\nu _{l}} \\
&=& \frac{\partial \omega _{ \mu _{1} \cdots \mu _{k}}}{\partial x^\rho} \xi _{ \nu _{1} \cdots \nu _{l}} \text{d} x^{\rho} \wedge \text{d} x^{\mu _{1}} \wedge \cdots \wedge \text{d} x^{\mu _{k}} \wedge \text{d} x^{\nu _{1}} \wedge \cdots \wedge \text{d} x^{\nu _{l}} \\
&& + \omega _{ \mu _{1} \cdots \mu _{k}} \frac{\partial \xi _{ \nu _{1} \cdots \nu _{l}}}{\partial x^\rho} \text{d} x^{\rho} \wedge \text{d} x^{\mu _{1}} \wedge \cdots \wedge \text{d} x^{\mu _{k}} \wedge \text{d} x^{\nu _{1}} \wedge \cdots \wedge \text{d} x^{\nu _{l}} \\
&=& \frac{\partial \omega _{ \mu _{1} \cdots \mu _{k}}}{\partial x^\rho} \xi _{ \nu _{1} \cdots \nu _{l}} \text{d} x^{\rho} \wedge \text{d} x^{\mu _{1}} \wedge \cdots \wedge \text{d} x^{\mu _{k}} \wedge \text{d} x^{\nu _{1}} \wedge \cdots \wedge \text{d} x^{\nu _{l}} \\
&+& ( -1)^{k} \omega _{ \mu _{1} \cdots \mu _{k}} \frac{\partial \xi _{ \nu _{1} \cdots \nu _{l}}}{\partial x^\rho} \text{d} x^{\mu _{1}} \wedge \cdots \wedge \text{d} x^{\mu _{k}} \wedge \text{d} x^{\rho} \wedge \text{d} x^{\nu _{1}} \wedge \cdots \wedge \text{d} x^{\nu _{l}} \\
&=& \text{d} \omega \wedge \xi + ( -1)^{k} \omega \wedge \text{d} \xi. \, \, \, \square
\end{eqnarray}
証明はすべて縮約記法でやりました。
「何この証明?意味不明」という人は飛ばしてもらっても構いません。
ただ、
\[ \mathrm{d}(\omega \wedge \xi) = \mathrm{d} \omega \wedge \xi + ( -1)^k \omega \wedge \mathrm{d} \xi. \]
という公式は微分幾何で頻出するので覚えておいてください。
これは「外微分のライプニッツ則」といいます。
\( \mathrm{d}^2=0 \) について 次は外微分の特に重要な特徴のひとつ、\( \mathrm{d}^2=0 \) を説明します。
正確に言えばこうです:
定理
任意の微分形式 \(\omega\) に対して次が成り立つ:
\[ \mathrm{d}(\mathrm{d} \omega) = 0. \]
つまり、どんな微分形式でも2回外微分をすれば \(0\) になるというわけです。
\( \mathrm{d}(\mathrm{d} \omega) = \mathrm{d}^2 \omega \) と略記されます。
試しに問題を解いてみましょう。
問題
\( \omega= -y \mathrm{d} x + x \mathrm{d} y \) に対して \(\mathrm{d}^2 \omega\) を計算せよ。
解答
先の問題より \( \mathrm{d} \omega = 2 \mathrm{d} x \wedge \mathrm{d} y.\)
よって
\begin{eqnarray}
\mathrm{d}^2 \omega &=& \mathrm{d}(\mathrm{d} \omega) \\
&=& \mathrm{d} (2 \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y) \\
&=& \mathrm{d}(2) \wedge \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \\
&=& 0.
\end{eqnarray}
このように、どんな微分形式であっても \(\mathrm{d}^2 \omega =0 \) となります。
証明しましょう。
問題
任意の微分形式 \(\omega\) に対して \(\mathrm{d}^2 \omega=0\) を示せ。
解答
局所座標で明示的に書き下す。
\begin{eqnarray}
\text{d}(\text{d} \omega) &=& \text{d} \left( \text{d} \left( \omega _{\mu _{1} \cdots \mu _{k}} \text{d} x^{\mu _{1}} \wedge \cdots \wedge \text{d} x^{\mu _{k}} \right) \right) \\
&=& \text{d} \left( \frac{\partial \omega _{\mu _{1} \cdots \mu _{k}}}{\partial x^{\nu}} \text{d} x^{\nu} \wedge \text{d} x^{\mu _{1}} \wedge \cdots \wedge \text{d} x^{\mu _{k}} \right) \\
&=& \frac{\partial^{2} \omega _{\mu _{1} \cdots \mu _{k}}}{\partial x^{\nu} \partial x^{\rho}} \text{d} x^{\rho} \wedge \text{d} x^{\nu} \wedge \text{d} x^{\mu _{1}} \wedge \cdots \wedge \text{d} x^{\mu _{k}}
\end{eqnarray}
ここで偏微分の順番を入れ替えても変わらないので、\(\text{d} x^{\rho} \) と \(\text{d} x^{\nu}\) を交換できる。
したがって \(\text{d}^2 \omega = -\text{d}^2 \omega\) であるから \(\text{d}^2 \omega =0. \, \, \, \square \)
この性質も微分幾何で活躍します。
頭に入れておいてください。
外微分とベクトル解析の関係 ここまでで外微分について書いてきましたが、「なんの役に立つの?」と思われるかもしれません。
そこで外微分とベクトル解析の関係を見ていくことにします。
まずは勾配(grad)です。
スカラー関数 \(f(x,y,z)\) の勾配は次で表されましたね:
\[ \nabla f = \left( \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) \]
これは\(0\)-形式の外微分と対応できます。
\(0\)-形式 \(f(x,y,z)\) を外微分すると
\[ \mathrm{d}f = \frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}y+\frac{\partial f}{\partial z}\mathrm{d}z \]
となります。
これは勾配とそっくりですね。
次に回転(rot)との関係を見ましょう。
ベクトル場 \( \boldsymbol{A}=(A_x, A_y, A_z) \) の回転は次で表されました:
\[ \nabla \times \boldsymbol{A} = \left( \frac{\partial A_z}{\partial y}-\frac{\partial A_y}{\partial z}, \frac{\partial A_x}{\partial z}-\frac{\partial A_z}{\partial x}, \frac{\partial A_y}{\partial x}-\frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \]
これは\(1\)-形式の外微分と対応できます。
問題
\(1\)-形式 \(A_x \mathrm{d}x+A_y \mathrm{d}y+A_z \mathrm{d}z\) の外微分を求めよ。
解答
\(\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}x=0\) および \(\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d} y = -\mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}x\) と線形性より
\begin{eqnarray}
\mathrm{d}(A_x \mathrm{d}x+A_y \mathrm{d}y+A_z \mathrm{d}z) &=& \mathrm{d} A_x \wedge \mathrm{d}x+\mathrm{d} A_y \wedge \mathrm{d}y+\mathrm{d} A_z \wedge \mathrm{d}z \\
&=& \left( \frac{\partial A_x}{\partial y} \mathrm{d}y + \frac{\partial A_x}{\partial z} \mathrm{d}z \right) \wedge \mathrm{d}x+\left( \frac{\partial A_y}{\partial x} \mathrm{d}x + \frac{\partial A_y}{\partial z} \mathrm{d}z \right) \wedge \mathrm{d}y+\left( \frac{\partial A_z}{\partial x} \mathrm{d}x + \frac{\partial A_z}{\partial y} \mathrm{d}y \right) \wedge \mathrm{d}z \\
&=& \left(\frac{\partial A_z}{\partial y}-\frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z+\left(\frac{\partial A_x}{\partial z}-\frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x+\left(\frac{\partial A_y}{\partial x}-\frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.
\end{eqnarray}
これは回転の式と全く一緒ですね。
このように、ベクトル解析と微分形式は密接に関わっているのです。
発散(div)に関してはレベルが高くなるので今回は省略します。
興味のある人は調べてみてください。
<追記>
ホッジ作用素の記事を書きました。
発散(div)の解説もしてます。
最後に 今回は微分形式の外微分について解説しました。
外微分は初めはとっつきにくくて難しそうに思えますが、いくつか具体的な計算をするとすぐに慣れるはずです。
外微分と言っても所詮は全微分の一般化です。
ただ、そこから勾配や回転といったベクトル解析の式が自然に現れるのは美しいですね。
微分幾何は一般相対性理論やゲージ理論にも通じる、現代科学を支える重要な分野です。
他の分野との関連も調べながら勉強していくと楽しいかもしれません。
では。
今回参考にした書籍↓