
夜空に広がる無数の星々。
その美しさに思わず息をのんだ経験、きっと多くの人にあるのではないでしょうか。
そんな感動の瞬間を写真という形で残したいと思うのは自然なことです。
しかし「星を撮るには特別な機材が必要なんじゃないの?」「赤道儀がないと無理なのでは?」と思って諦めてしまっている人も少なくありません。
実は赤道儀がなくても、初心者でも工夫次第で十分に美しい星景写真を撮ることができるんです。
しかも星空と一緒に地上の風景を取り入れる星景写真なら、むしろ赤道儀なしの方が構図が作りやすいというメリットもあります。
この記事では星空撮影を始めたい初心者の方に向けて、赤道儀を使わない星景写真の撮影方法をわかりやすく解説します。
星空撮影の第一歩を自信を持って踏み出せる内容になっています。
ぜひ最後までご覧ください。
Contents
星景写真とは?星と風景が織りなす幻想的な世界
星景写真とは夜空に輝く星と、地上の風景を同時に写し込んだ写真のことです。
地上の風景が写っていれば「星景写真」で、地上の風景が写っていなければ「天体写真」と区別されます。
今回取り扱うのは地上の風景を一緒に写す星景写真です。
山の稜線や木々のシルエット、街の灯りや建物の輪郭といった地上の風景と遥か彼方の星々の光が一枚の写真に収まります。
そこには言葉では表せないようなドラマが生まれるはずです。
一方、天体望遠鏡などで星雲や銀河を拡大して撮る「天体写真」は精密な赤道儀や高度な知識が必要で敷居が高いです。
しかし星景写真は三脚とカメラ、そして夜空への好奇心さえあれば誰でも挑戦できる奥深い世界です。
しかも星景写真には「その場所ならではの情景を記録できる」という魅力があります。
天体写真はどこから撮っても同じですが、星景写真はその時のその場所だけの風景が記録されます。
時には雲が邪魔することもあるかもしれませんが、雲間からきらめく星々も大自然のひとつです。
旅先で見上げた夜空、地元の山から見える星座、いつもの帰り道の夜空のきらめき。
それらすべてが星景写真という作品になります。
そう考えると星景写真は奥深いですよね?
星景写真を撮るための機材
まず気になるのが星景写真を撮る時の機材だと思います。
具体的にはカメラ、レンズ、三脚が必要です。
カメラ(一眼レフまたはミラーレス)
最近はスマホで星景写真に挑戦する方も増えてきました。
ですが私はスマホで星景写真を撮ったことがないので詳しくは書けません。
私はiPhoneを持っているのですが、iPhoneSEだと全く星景写真が撮れませんでした。
星景写真は Google Pixel がすごくいいらしいです。
そんな話は置いておいて、本格的に星景写真を始めるならカメラを1台持っておくといいでしょう。
最近は Canon, Nikon, Sony の3つのメーカーが強いですが、私はNikonを使ってます。
中でも Nikon Z6II が一番性能が良く、コスパもいいと思います。
詳しくはこの記事をどうぞ。
レンズ
カメラ以上に大切なのがレンズかもしれません。
レンズについては後述しますが、基本的にはメーカー純正かSigmaのレンズを選べば間違いはないと思います。
Sigmaは価格が少し安めなので性能が悪いだろうと思われる方もいるかも知れませんが、純正を凌ぐ性能を持ったレンズも数多く存在しています。
詳しくは調べてみてください。
ただ、Nikonのミラーレスカメラ(Zマウント)なら NIKKOR Z 20mm f/1.8S 一択です。
詳しいレビューはこちらに書きました。
三脚
三脚も想像以上に大事で、カメラとレンズを支えられる強いものが必要になります。
特に海沿いだと、やわな三脚だと強風で揺れたり飛ばされたりしてしまいます。
最近は軽くて丈夫なカーボン三脚が人気です。
私が使っているのは Velbon UT-3AR です。
軽くて丈夫なのでおすすめですよ。
赤道儀なしで星を撮るためのカメラ設定
赤道儀なしでも星景写真を撮る方法は「星があまり動かないうちにシャッターを切る」というものです。
地球の自転により、24時間で星は一周します。
なので星は1時間で15°動きます。
1分で0.25°です。
「たかが0.25°じゃん」と思われるかもしれませんが、ひとつひとつの星を鮮明に記録する星景写真では0.25°も命取りになるのです。
なので、星が大きく動く前にシャッターを切れば星がブレずに写せるというわけです。
シャッターを切っている時間のことをシャッタースピード(SS)と言います。
目安は10秒から20秒でしょう。
ですがここでもうひとつ重要な考え方があります。
たとえば私たちが新幹線に乗ったとき、小さいもの(家や木など)はものすごいスピードで動いていきますが、大きいもの(山や雲など)はそれほど速くは動かないですよね。
星空も似たような感じで、夜空を拡大すると星がものすごいスピードで動いていきます。
一方、夜空全体を写している場合は多少のズレも目立たなくなります。
その拡大率を表すのがレンズの焦点距離(単位はmm)です。
焦点距離が短いほど拡大率は低く、長いほどより拡大されるようになります。
なので星景写真では夜空全体を写せるレンズ(焦点距離が20mm前後)を使うのが一般的です。
しかし、星の光は非常に淡く暗いです。
10秒や20秒では全然星が写らないという場合もあります。
その場合にはf値とISO感度を確認しましょう。
まず、f値とはレンズの明るさを表す値です。
f値が低いほど明るくなります。
明るいということは短いシャッタースピードでも多くの光を取り込むことができるようになり、星景写真で非常に有利になります。
目安はf1.8からf2.8です。
f4でも撮れないことはないですが、その場合赤道儀が欲しくなってしまいます。
赤道儀を使わない場合はレンズに投資をするようにしましょう。
もうひとつ、ISO感度というものがあります。
これは取り入れた光を電気信号としてどれだけ増幅するかという値で、ISO感度が高いほど写真が明るくなります。
ただISO感度は実際の光を増幅しているだけなので、上げまくればいいというわけではありません。
ISO感度を上げるとその分ノイズも一緒に増幅されてくるので、元のf値とシャッタースピードが悪いとノイズまみれになってしまいます。
ですが赤道儀を使わない撮影なので、シャッタースピードは20秒以下が望ましいです。
そうなるとf値を明るくするしかないんですよね。
なので赤道儀なしで星景写真を撮る最大のコツは「f値の低いレンズを使うこと」です。
ただ、f値が低いだけの粗悪品のレンズだと星の周りに紫色のリングが発生したり、四隅の星が矢印のようにいびつに引き伸ばされる現象が起きます。
レンズを買う際は必ずレビューを見て星景写真に合ったものかチェックしましょう。
ちなみに、Nikon Zマウントなら NIKKOR Z 20mm f/1.8 S がダントツでおすすめです。
CanonやSonyのカメラならSigmaのレンズを検討してみるのもいいと思います。
また、星景写真では基本的にマニュアルモード(M)が基本になります。
f値を決めるのも手動、SSを決めるのも手動、ISOを決めるのも手動、ピントを合わせるのも手動です。
最初は慣れないかもしれませんが、そのうち自分で考えてできるようになってきます。
私が好きな設定は f値 1.8, SS 10秒、ISO 3200 です。
それ以外にも自分で好きな設定を試してみてください。
そしてもうひとつ、星景写真は画像処理も大きな醍醐味です。
あとから設定を自由にいじれるよう、RAWフォーマットで記録するようにしてください。
やり方が分からなければ調べてください。
撮影に適した時間帯と場所の選び方
星空を美しく撮るためには「いつ・どこで撮るか」が非常に大切です。
星の光は想像以上に淡くて暗いです。
明るい街中や月が出ている夜は星が見えにくくなってしまいます。
理想的な条件は以下の通りです:
・月明かりのない新月前後の夜
・街灯の少ない郊外や山、海辺
・空気が澄んだ日 (花粉や黄砂はNG)
・夏の天の川を狙うなら3-5月の夜明け前
場所選びには光害マップが参考になります。
最近はスマホアプリ(Sky Guide)で撮影シミュレーションができるため、事前にしっかり準備しておくと当日の撮影がスムーズになります。
天気予報はYahoo天気やWindy, 星空指数を見るのがいいでしょう。
詳しくはこちらの記事を見てください。
星景写真を印象的にする構図の工夫
星景写真は単に空を撮るのではなく、「星と風景のバランス」を意識することが大切です。
特に意図がない場合、星景写真は地面に対して水平に撮ると一番綺麗に見えます。
私の使っている Nikon Z6II だとカメラの角度を自動検知し、水平だと黄色の線が緑色になる機能があってとても便利です。
夜空を大きく写す中に地上の風景を入れることで、作品にスケール感が生まれます。
また、最近はSNSの影響で縦構図が非常に人気です。
従来の横向きの構図にとらわれず、カメラを縦にして撮影してみてはいかがでしょうか。
その場合はSmallRigのL字型ブラケットが非常に便利です。
また、以下のようなアイデアが構図の参考になります。
・木や建物のシルエットを前景に
・山の稜線を斜めに横切らせてダイナミックに
・湖や水面に星を反射させて幻想的に
・階段を下から見上げて星空と一緒に
星座の配置や天の川の流れ方によっても構図の印象は大きく変わります。
いろいろな角度や距離で何枚も撮ってみると、自分の好きなスタイルが見えてきます。
現像で仕上げる。星景写真は撮って終わりじゃない
星景写真は撮るだけでなく「仕上げる」ことも楽しみのひとつです。
RAWで撮影した写真を現像ソフトで調整することで印象を大きく変えることができます。
特に調整したいポイントは以下の通りです。
・露出:暗すぎた場合に明るく補正
・コントラスト:星のキラキラ感を強調
・ホワイトバランス:青系にするか、暖色系にするかで印象が変わる
・シャドウ・ハイライト:地上の風景を浮かび上がらせる
・ノイズ軽減とシャープネス:星をくっきり見せる
仕上げ作業を通して「自分らしい星空表現」ができるようになると、撮ること自体がもっと楽しくなります。
Photoshop の Camera RAW で現像するのもいいと思いますが、サブスクの値段が高いですよね。
なので私は買い切り型の Affinity Photo 2 を推しています。
Photoshopと遜色ないレベルでRAW現像ができるのでおすすめです。
赤道儀が必要になるのはどんなとき?
では、赤道儀が本当に必要になるのはどんなときでしょうか?
実は、以下のようなケースでは赤道儀の導入を検討すべきです。
・星を長時間露光(30秒以上)で点像のまま撮りたい
・望遠レンズで星雲や星団を拡大して撮影したい
・星だけを純粋な天体写真として狙いたい
・地上の風景と夜空を別々に撮って合成する「新星景写真」に挑戦したい
赤道儀は地球の自転に合わせてカメラを動かしてくれる装置です。
これにより星が動いて流れてしまうのを防げます。
ただし、使いこなすには設置や極軸合わせなど、やや手間がかかります。
「もっと本格的に天体写真を撮ってみたい」と思ったときに、次のステップとして検討するといいでしょう。
まずは赤道儀なしでの星景写真に慣れてからでも十分に間に合います。
星景写真のマナー
最後に伝えたいことがあります。
鉄道写真や野鳥撮影でも、最近はマナーの悪い人たちが増えて問題になっています。
本来は魅力のある趣味が一部の人達の身勝手な言動により馬鹿にされてしまうのは許せないです。
星景写真でもマナーの悪い人たちが増えないよう、以下のことに気をつけていただければと思います。
レーザーポインターの使用は周囲への配慮を忘れずに
星の光は非常に暗く淡いです。
人工の光は周囲の人の迷惑になることがあります。
星の位置を指し示すのに便利なレーザーポインターですが、夜間の撮影現場では非常に目立ちます。
暗闇でカメラの露光中にレーザーが横切ると、他の人の写真に線が写り込んでしまうこともあります。
使用する場合は周囲に誰かが撮影していないかを確認し、一声かける配慮が大切です。
また、高出力のレーザーポインターをむやみに使うと航空機に影響を与えることがあります。
法律により規制されているレーザーポインターは使っていけません。
風景を不自然にライトアップしない
星景写真で風景を際立たせたいとき、懐中電灯やストロボで風景を照らすライトアップを使いたくなることがあります。
しかし人工的な光で風景を明るく照らすと他の撮影者の作品に光が入ったり、生態系に害を与える場合があります。
有名な写真家でも地上の風景を不自然に照らしている人がいますが、私はよくないことだと思います。
最近では後から画像処理で地上部分を持ち上げることが十分可能です。
撮影時の照明は最小限にとどめることをおすすめします。
無灯火走行は危険!足元灯りは必須
人工の明かりは最小限がいいのはもちろんですが、安全のための明かりは必要です。
星をきれいに撮るために「完全な暗闇がいい」と考えて、ライトを使わずに歩いたり自動車で移動したりする人がいますが非常に危険です。
過去に無灯火走行で転落する死亡事故が発生しています。
絶対にやめてください。
足元を照らす赤色LEDやヘッドライトなどを使って安全第一で行動しましょう。
赤色ライトは目が暗闇に慣れた状態(暗順応)を保てるので、天体観察や撮影に適しています。
ただ、非常に明るい懐中電灯で遠くまで照らすのはやめたほうがいいです。
車のライトもハイビームではなくロービームで、必要十分に留めるのをおすすめします。
私有地には絶対に無断で入らない
見晴らしの良さそうな場所があっても、そこが私有地や立入禁止区域である場合は絶対に入ってはいけません。
土地の所有者に迷惑をかけたり、通報されるケースもあります。
どうしても使いたい場合は事前に所有者に許可を取るしかありません。
撮影スポットを探すときは事前に地図や情報を確認し、公的に立ち入り可能な場所だけを選ぶようにしましょう。
地域の人と良好な関係を保つことも長く星空を楽しむためにとても大切です。
他の撮影者への理解と尊重を忘れずに
夜の静かな場所では天体写真を撮っている人も少なくありません。
天体写真は星を何時間もかけて追尾しながら撮影するため、ほんの少しの光でも大きな影響を受けてしまいます。
大きな赤道儀の上に望遠鏡を積んでいる人がいたら、その人は天体写真を撮っている人です。
その場に他の撮影者がいたらライトの使用を最小限にしたり、会話を控えめにするなどの配慮を心がけましょう。
相手がどんな目的でそこにいるのかを理解しようとする姿勢が、お互いの撮影体験をよりよいものにします。
作例
ここまで色々書いてきましたが、実際の作例を見ないとつまらないですよね。
というわけで私が赤道儀なしで撮った星景写真を並べてみました。
使用機材は Nikon Z6II と NIKKOR Z 20mm f/1.8 S です。
設定は f1.8, SS 10秒、ISO 3200 です。
ケンコーのプロソフトンフィルターを使ってます。





赤道儀がなくても星空は撮れる
星景写真の魅力は機材の有無に関係なく、空を見上げる気持ちから始まります。
赤道儀がなくても、カメラと三脚とほんの少しのコツがあれば誰でも夜空を写真に残すことができます。
最初の一枚はピントが合っていなかったり、星が流れていたりするかもしれません。
ですがその小さな失敗が次の撮影をもっと楽しくしてくれます。
星空は毎晩違った表情を見せてくれます。
流星群や惑星、オーロラといった、その時でしか再現できない写真も撮れます。
場所を変え季節を変え、時間を変えれば見える星も構図もすべてが新しい体験になります。
ぜひ、あなたも今日から星景写真の旅を始めてみませんか?
夜空を見上げ、シャッターを押すその時間はきっと忘れられないものになるはずです。
では。



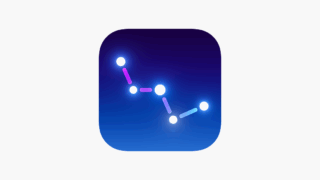























非常に参考になりました。
ありがとうございますm(*_ _)m