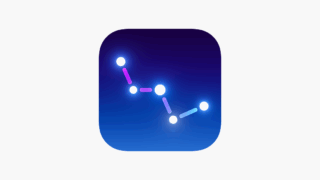よく「月と金星が接近!」とか「月とすばるが接近」とか聞きませんか?
もしくは月が夜空にいて、「月が邪魔だけど目標の天体から60°以上は離れていてほしいな…」という場面もあるかもしれません。
そんなときに、2つの天体がどれくらい離れているかを表す角度(離角)が計算できると非常に便利です。
というわけで、今回は2つの天体の離角を計算する方法を解説します。
まずは赤経と赤緯を知る必要がある
まず、計算の前に天体の座標を知らないといけないですよね。
そこで役立つ座標が赤道座標系です。
詳しくはこの記事で解説してます。
赤経・赤緯とは、観測者の位置や時刻に関係なく天体の位置を表せる便利な座標です。
赤経は0hから24hまであり、1hで15°を表します。
また、60mで1hを表します。
なので例えば4h20mは65°です。
一方、赤経軸に直行する形で赤緯軸があり、これは-90°から+90°までです。
赤緯+90°が天の北極(北極星の近く)で-90°が天の南極(はちぶんぎ座あたり)を表します。
また、60’で1°を表します。
‘は分または分角と読みます。
なので、例えば+30°15’は+30.25°です。
この2つの角度によりすべての天体の座標が表されるというわけです。
実際の天体の赤経赤緯はプラネタリウムアプリで簡単に知ることができます。
iOSユーザーなら Sky Guide がおすすめです。
難しそうなのでとりあえず計算機を作ってみました!
離角計算ツール(赤経は時分、赤緯は度分)
<2025/8/15 追記>
赤緯の符号が選べない問題を解決しました。
計算式の説明
さきほどの計算機のコードはChatGPTに書かせました笑
私はプログラミングは全くできません。
さて、ここからは計算機の仕組みを知りたい人向けに説明していきます。
どうやって離角を計算するのかというとこの式を使います:
ここで \( \delta_1, \delta_2 \) は天体1,2の赤緯、 \( \alpha_1, \alpha_2 \) は天体1,2の赤経、 \( \theta \) は2つの天体の離角です。
結構難しそうですね。
ここで大学数学ではおなじみの球座標というものがあります。

球座標とは、半径 \(r\) の球の表面の座標を3次元ユークリッド空間の座標 \( (x,y,z) \) では次のように表せるというものです:
ここで \(0 \leq \theta \leq \pi \) は天頂角を表し、\( 0 \leq \phi < 2\pi \) は方位角を表します。
天頂角 \( \theta \) とは、 \(z\) 軸の正の方向から測った \(z\) 軸と座標のベクトルの角度のことです。
方位角 \(\phi\) は座標ベクトルを \(xy\) 平面に正射影したものと \(x\) 軸の角度(反時計回りに測られる)のことです。
詳しいことはwikipediaを見てください。
ただ、ここでひとつ問題があります。
方位角はそのまま赤経と対応させられるのですが、天頂角の測り方が赤緯と違うのです。
そこで関係式 \(\delta = \dfrac{\pi}{2}-\theta \) を使いましょう。
そうすると、天文学における球座標は次のように書き換えられます:
\( -\dfrac{\pi}{2} \leq \delta \leq \dfrac{\pi}{2} \) は赤緯、 \( 0 \leq \alpha < 2\pi \) は赤経です。
今は半径を \(1\) とする単位球で考えると、
ですね。
天体1の座標は
であり天体2の座標は
で表されます。
両方とも単位ベクトルであり、両方の内積が \(\cos \theta\) になることから
最後の等式では加法定理を逆に使いました。
これで証明が終わりましたね。
球座標を少し変形して内積を取っているだけなので大学数学を経験した人なら簡単だったかもしれませんが、高校数学までの知識だと少し厳しいです。
まあこんなこと知ってても計算結果には影響しないのですが笑
2つの天体の離角を求めたくなったらこのページに来てください。
ブックマーク・拡散もよろしくお願いします。