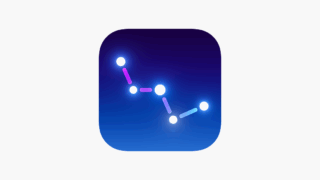私たちが夜空を見上げるとき、目にする星の多くは天の川銀河の中にある恒星たちです。
しかしはるかその向こう側、数千万光年以上の彼方には無数の銀河が広がっており、それぞれが独自の進化の歴史をたどっています。
そのような銀河の海の中にあって、まるで人工的に並べられたかのように直線に並ぶ銀河群が存在することをご存知でしょうか?
それが今回紹介するマルカリアンチェーン (Markarian’s Chain) です。
別名マルカリアンの鎖とも呼ばれていますが、多くの銀河が鎖のように連なって見えることからその名がつきました。
Contents
マルカリアンチェーンの写真
まずはマルカリアンチェーンが実際にどんな見た目をしているのか見てみましょう。
こんな感じです。

これは私が横浜市内から撮影した画像です。
暗い場所から撮影すればもっときれいに映るはずですが、いずれ撮り直したいと思います。
この写真に写っている白っぽい楕円形や細長いものはすべて銀河です。
見ての通り、複数の銀河が鎖のように連なっている様子がわかります。
なかなか面白い見た目をしていますね。
私が初めてマルカリアンチェーンの写真を見たとき、色々な銀河が集まっている様子に感動しました。
ひとつの銀河だけでも数千億の星があるのに、それが複数集まっているわけです。
ものすごいスケールの話だと思いませんか?
マルカリアンチェーンとは?
マルカリアンチェーンはおとめ座銀河団の中にある銀河群で、十数個の銀河が鎖のように連なって見える構造を指します。
この構造は天文学者のベンジャミン・マルカリアン (Benjamin Markarian) によって1960年代に注目されました。
彼はこの直線的な銀河の並びが偶然ではなく、何らかの物理的関係に基づく可能性があると考えて観測と研究を行いました。
その結果、これらの銀河が共通する固有運動をしていることを突き止めました。
固有運動とは宇宙空間での私たちから見た「奥行き」を考慮せず、私たちから見える上下左右の動きだけに注目したものです。
この「チェーン」は肉眼では見えませんが、天体写真では非常に印象的な姿をしています。
さっきの写真のように、大きくて明るい銀河群なのでアマチュア天文家でも簡単に撮影できます。
眼視でも大口径(20cmくらい)の望遠鏡を使えばいくつかの銀河が視野内に同時に捉えられるみたいです。
銀河団とその中の「秩序」
おとめ座銀河団は地球から約5300万光年離れた場所に位置する、地球から非常に近い大規模な銀河団です。
数千もの銀河がこの銀河団に属しており、その中心には巨大楕円銀河M87がいます。
M87は強力な電波やX線を放出していることで有名で、最近では中心にある超巨大ブラックホールM87*がEHTにより観測されました。
M87*は直接観測されたブラックホールとしては初めてです。
マルカリアンチェーンはおとめ座銀河団のほぼ中心に位置していて、おとめ座の領域に含まれます。
実際の空間的な関係は完全に解明されていないものの一部の銀河は重力的に相互作用していると考えられており、銀河団の形成と進化の過程を読み解く重要な鍵となっています。
主な構成銀河と最新の研究成果
マルカリアンチェーンに含まれる銀河は10個以上ありますが、以下の銀河が特に注目されています。
最近の研究成果を交えて紹介します。
M84
M84はマルカリアンチェーンの中にある楕円銀河です。
1957年, 1980年, 1991年の3回にわたって超新星が観測されています。
中心には太陽の30億倍ほどの質量のブラックホールがあるとされています。
M86
M86も楕円銀河です。
面白いことに、M86はおよそ244km/sという猛烈なスピードで天の川銀河の方に向かってきています。
メシエ天体の中でも最も大きな青方偏移を示していると言われています。
赤方偏移は天体が天の川銀河から遠ざかっているときに見られる現象ですが、青方偏移はその逆の場合に見られる現象です。
M86は楕円銀河にしては通常考えられない量の星間塵を持っており、非常に質量が大きいとされています。
またM86は他の小さな銀河を「食べている」らしく、星間物質を吸収してジェットを吸い込んでいるみたいです。
NGC4435とNGC4438
このペアは “Eyes Galaxies” と呼ばれていて、ひしゃげた銀河と星間ストリームが特徴です。
ネットには綺麗な画像が山ほどあがってるので後で調べてみてください。
この人の作品は特にきれいだと思います。
なんでこんな面白い形をしているのか諸説ありますが、2つの銀河が重力で引かれ合って星間物質が剥ぎ取られたのではないかと言われています。
このように、重力で引かれ合っている複数の銀河は相互作用銀河と呼ばれています。
NGC4438はNGC4435だけでなく、X線観測でM86とのガスのつながりも見られています。
もしかしたら昔にM86が高速で通過していったときの名残なのかもしれません。
またNGC4438の中心には活動銀河核があるとされていて、天文学の研究の対象になっているそうです。
中々面白そうなので今度撮ってみたいと思います。
直線状の並びは偶然か、それとも必然か?
マルカリアンチェーンのように銀河が直線状に並ぶ現象は一見すると人工的にすら感じられます。
現代天文学ではこの整列はただの見かけ上そう見えているだけの偶然と考えられていますが、それだけでは説明しきれない部分もあります。
宇宙には「フィラメント構造」と呼ばれる、銀河が網目状に集まる重力的な骨組みが存在します。
マルカリアンチェーンの銀河の一部は、実際にそのようなフィラメントの一部を構成している可能性があり、整列の背景には宇宙の大規模な構造形成が関与していると考える研究者もいます。
実際に観測してみよう
マルカリアンチェーンはおとめ座にあります。
春の夜空(3月から5月)に見ることができます。
その頃におとめ座が南中する深夜0時ごろが最も観測に適しています。
個々の銀河を観測したい場合はできるだけ口径が大きな望遠鏡を使うといいです。
口径20cmくらいがいいと思いますが、10cmほどでも問題なく観測できます。
観測する際には街明かりの少ない場所(光害の少ない郊外や高地)を選ぶのが大切です。
また銀河は淡く、月明かりにもかき消されてしまいがちなので新月期を選びましょう。
見つけるときはヴィンデミアトリクス (Vindemiatrix) という、黄色っぽくて明るい星が目印になります。
そこから北西に辿るように望遠鏡を動かすとM84とM86のペアが視界に入るはずです。
そこを起点に、東へ向かってNGC4438, NGC4435などの銀河を順に追いながらチェーン構造をたどってみましょう。
詳しい位置関係は Sky Guide で調べるのがおすすめです。
おわりに
マルカリアンチェーンは偶然と必然が織りなす宇宙の設計図を垣間見ることのできる貴重な構造です。
そこには銀河同士の引力、ガスの流れ、星の誕生や消滅といった、壮大な時間スケールの物語が刻まれています。
そして私たちはその一部を望遠鏡越しに体験することができます。
最新の研究によりその背後にある科学的メカニズムが少しずつ明らかになってきましたが、それでもなおこの「銀河の鎖」には多くの謎が残されています。
この春、ぜひ夜空を見上げて自分の目で銀河たちを観察してみてください。
では。