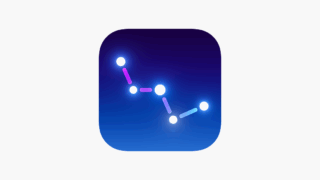夜空の中でもっとも有名な銀河のひとつ、それが**アンドロメダ銀河(M31)です。
地球からおよそ250万光年というとてつもない距離にあるにもかかわらず、条件がよければ肉眼でもぼんやりと見ることができます。
肉眼で確認できる数少ない銀河のひとつですね。
写真に撮るとこんな感じです。

というわけで、今回はアンドロメダ銀河をスターホッピングで探す方法を解説します。
双眼鏡や望遠鏡でも使える技なので、ぜひ参考にしてみてください。
Contents
アンドロメダ銀河ってなに?わかりやすく解説
アンドロメダ銀河(M31)という名前を聞いたことはあっても、それがどんな天体なのか、どこにあるのか、どうしてそんなに有名なのか――詳しく説明できる人は意外と少ないかもしれません。
実はアンドロメダ銀河は夜空を見上げたときに地球から肉眼で見える数少ない銀河であり、しかも私たちの銀河系の天の川銀河と将来的に衝突する運命にある特別な天体なんです。
そもそも「銀河」とは、何千億・何兆個という星や無数のガスが重力で集まって光っている天体です。
私たちの太陽系も「天の川銀河」と呼ばれる渦巻銀河の一員で、星やガス、塵と一緒に宇宙空間を回っています。
そしてアンドロメダ銀河もまた同じように無数の恒星を抱えた巨大な銀河であり、天の川銀河の隣人にあたる存在です。
私たちからの距離は、なんと約250万光年。
光の速さで飛んでも250万年かかるという気の遠くなるような距離にあります。
それでも条件がそろえば肉眼で見えてしまうほど明るく大きいという点で、アンドロメダ銀河は観察対象として非常に特別な天体といえるでしょう。
では、なぜそれほど大きくて明るいのでしょうか?
それは、アンドロメダ銀河のスケールがとてつもないからです。
直径はおよそ22万光年にも及び、天の川銀河(約10万光年)を大きく上回ります。
さらに内部には太陽のような恒星が1兆個以上あると推定されており、その数は天の川銀河の3倍くらいとも言われています。
これだけ巨大な銀河が比較的近い位置にあるため、私たちの目にも届くのです。
見た目としては中心が明るく、周囲が淡く広がる楕円形の光の塊に見えます。
満月の6倍もの大きさがあるとされますが、実際の空で見ると周縁部は非常に淡いため肉眼ではそこまで大きくは見えません。
それでも、双眼鏡を使えば宇宙の向こうに浮かぶ別の世界をリアルに感じることができるのです。
アンドロメダ銀河が特別なのは、見た目や大きさだけではありません。
私たちの天の川銀河と、約50億年後に衝突すると言われている天体でもあります。
これは重力によってお互いに引き寄せ合っているためで、現在アンドロメダ銀河は約110km/sのスピードで地球に向かって接近しているのです。
衝突と聞くと破壊的なイメージがありますが、星と星の間にはとても広い空間があるため、実際にぶつかるというよりは2つの銀河がゆっくりと融合していくイメージになります。
最終的にはどちらの形も失われ、楕円銀河のような新たな銀河が誕生するだろうと考えられています。
このように、アンドロメダ銀河は単なる観察対象というだけではなく、宇宙の成り立ちや未来を考える手がかりにもなる非常に重要な天体なのです。
そして何よりも素晴らしいのは、そんな壮大な銀河が今この瞬間も夜空に静かに浮かんでいるという事実です。
アンドロメダ銀河は宇宙を感じるきっかけとしてこれ以上ない存在です。
星座の知識がなくても、望遠鏡を持っていなくても、まずは名前を覚えてみてください。
秋の澄んだ夜に星の並びを頼りにたどっていけば、私たちのご近所さんを見つけることができるでしょう。
見える時期と時間帯は?
アンドロメダ銀河は空さえ暗ければ地球から肉眼で見えるほど明るい、非常に珍しい系外銀河です。
とはいっても、肉眼ではぼやっとした光のもやのようにしか見えないですが。
それでも見れたらラッキーです。
ですが、見えるかどうかは「いつ観察するか」に大きく左右されます。
星空は季節によって見える星座や天体の位置が大きく変わるため、アンドロメダ銀河を見つけたいならまずは見頃の時期と時間帯を把握しておくことが非常に重要です。
ベストシーズンは秋!9月から11月が最適
アンドロメダ銀河の観察に最も適した時期は、毎年9月から11月ごろです。
この時期にはアンドロメダ銀河が早くから天高く昇ってくるので観察しやすくなります。
9月は0時、10月は22時、11月は20時くらいから観察を始めるといいでしょう。
特に10月は0時頃に南中(最も天高くに上がる)するので、一晩中観察できます。
アンドロメダ銀河は東京では最大84度と、南中のときには天頂の近くまで昇ってきます。
天頂とは真上のことです。
天頂近くにあるということは地平線近くに比べて大気の影響(ゆらぎや光害)を受けにくく、光害の影響も比較的少ないということです。
これは非常に大きな利点ですね。
また、秋は空気が乾燥しはじめ、夜空の透明度が高くなる時期でもあります。
夏場のようなもやや湿気が減り、いい条件で観察できるのもアンドロメダ銀河にとっては追い風です。
ただ9月は秋雨前線や台風がやってくるので、11月が一番天気が安定していると言えるでしょう。
何時ごろ見える?季節と南中時刻の関係
アンドロメダ銀河は、見える時期だけでなく時間帯によっても観察条件が大きく異なります。
基本的には、できるだけ空の高い位置に来ている時間帯を狙うのがベストです。
つまり、アンドロメダ銀河が南中しているときに観察するのが一番いいです。
というわけで、季節ごとの南中時刻をまとめてみました。
- 8月半ば:3時ごろ
- 9月初め:2時ごろ
- 9月半ば:1時ごろ
- 10月初め:0時ごろ
- 10月半ば:23時ごろ
- 11月初め:22時ごろ
- 11月半ば:21時ごろ
- 12月初め:20時ごろ
- 12月半ば:19時ごろ
見るだけなら8月半ばから12月半ばまでチャンスがありますが、じっくり観察したり撮影したい場合は10月や11月がいいでしょう。
光害と月明かりにも注意!
アンドロメダ銀河は非常に淡い天体であり、月明かりや都市の光害の影響を大きく受けます。
満月や街明かりの多い場所では、双眼鏡を使っても見えないことがあるほどです。
そのため、できるだけ新月前後の時期を狙うこと、また月が出ていない時間帯(例えば月が沈んだ深夜帯)を選ぶことが重要になります。
秋から冬は日没が早く、月の出入り時間と観察時間がぶつかりやすい季節なので、事前に月齢カレンダーやアプリで確認しておくと安心です。
おすすめのアプリは Sky Guide です。
Sky Guide ならアンドロメダ銀河の位置をその場でチェックできます。
iPhoneとiPadにしか対応していないのが惜しいですが。
Androidの人は Star Walk 2 がおすすめです。
アンドロメダ銀河の位置は?
というわけで、ここからはアンドロメダ銀河の位置を解説していきます。
*プラネタリウムの画面はすべて星図アプリ Sky Guide からとっています
アンドロメダ銀河の「アンドロメダ」とはアンドロメダ座のことで、アンドロメダ座にあることからアンドロメダ銀河と呼ばれるようになりました。
アンドロメダとは、ギリシャ神話では鎖に繋がれた王女のことを言います。
実際の夜空での位置はこんな感じです。

アンドロメダ座は”y”のような形をしています。
その左上に当たる部分のすぐ近くにアンドロメダ銀河がいます。
注目すべきはアルフェラッツとミラクという2等星たちです。
アルフェラッツはペガスス座とつながっていて、秋の四辺形の一部なので見つけやすいでしょう。
そこからミラクに辿っていき、星を辿っていけばアンドロメダ銀河にたどり着けます。
上の写真はかなりの誇張で、肉眼でそこまではっきり見えるわけではありません。
ただ、望遠鏡やカメラを使いながら探すとアンドロメダ銀河の中心部ははっきりと見えるでしょう。
アンドロメダ銀河の中心部は明るいとはいっても、普通の星とは違い広がりを持った球体のような見た目をしています。
なので見つけたときはすぐに「星じゃないな」とわかるはずです。
スターホッピングのしかた(その1)
ここから実際のスターホッピングのしかたを紹介します。
最初の目印となるのは、秋の四辺形です。

2等星が集まっているので、秋の四辺形はかなり明るいです。
天高くに四角形のように集まっている星々がいたら、それが秋の四辺形です。
その四辺形の中で、最もカシオペヤ座に近いものを探しましょう。
カシオペヤ座とはWマークで有名な星座で、非常に明るいので簡単に見つけることができます。
カシオペヤ座は北の空にいるはずです。
カシオペヤ座に最も近い秋の四辺形の星のひとつ、それがアルフェラッツです。

他の3つの星と比べて、アルフェラッツが一番カシオペヤ座に近いのがわかりますね。
アルフェラッツを見つけたらそこはもうアンドロメダ座です。
次に見つけるべきはミラクです。
アルフェラッツから東の方向に行くと、オレンジ色の星が見えるはずです。
それがアンドロメダ座デルタ星です。
そこから少し曲がって視野を動かしていくと、デルタ星よりもさらに明るいオレンジ色の星がいます。
それがミラクです。
そこから、アルフェラッツから辿って来た道から90度右に曲がってミラクから進んでいくと、白いひとつの星が見つかります。
それがアンドロメダ座ミュー星です。
そこからさらに同じ方向に進んでいくと、もうひとつ白い星がいるはずです。
それがニュー星です。
そこからさらにほんの少し進むと、ぼやっとした光のもやもやが見えるはずです。
それがアンドロメダ銀河です。
図にするとこんな感じです。

アルフェラッツ→デルタ星→ミラク→ミュー星→ニュー星→アンドロメダ銀河 の順でたどっていくとわかりやすいでしょう。
このやりかたが一番わかりやすいのですが、玄人向けのもうひとつのやり方も紹介します。
スターホッピングのしかた(その2)
2つ目の方法で使う目印はカシオペヤ座です。

その中でもオレンジ色の星、シェダルを使います。

これです。
このさらに北のほうにアンドロメダ銀河がいます。
具体的な辿り方はこんな感じです。

シェダルからゼータ星、クシー星、オミクロン星、パイ星を辿っていってください。
ゼータ星は明るいですが、他は5等星ですね。
それでも双眼鏡や望遠鏡なら5等星くらいは普通に見えます。
順番に辿っていけばアンドロメダ銀河にたどり着けるでしょう。
ただ、このやり方はかなり難しいです。
「おもしろそうだな」と思ったらこの方法も試してほしいですが、まずは方法その1をやってみてください。
双眼鏡の選び方はこちらで解説しています。
最後に
今回はアンドロメダ銀河の見れる時期、位置、探し方などを解説しました。
「秋の星空はつまんない」と思われるかもしれませんが、アンドロメダ銀河は面白いですよ。
一度は双眼鏡や望遠鏡でその姿を見てみてください。
また、撮影してみたいという方はこちらの記事も読んでみてください。
アンドロメダ銀河は私たちから最も近い渦巻銀河で、天文学的にも重要な存在です。
「もしかしたら宇宙人が住んでるかもしれない」と思って眺めていると楽しいかもしれません。
アンドロメダ銀河の住人もきっと、私たちの天の川銀河を見て同じようなことを思っているのでしょうね。
秋といえばアンドロメダ銀河。
ぜひ探してみてください。
では。